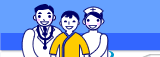法人・ブロックでの相互評価重要と
病院・診療所に続き薬局でも自己点検運動が進んでいます。ほとんどの薬局で自己点検が終了し、総括表の作成も5割になりました。03年11月に開催された薬局長研修会では、管理者に求められる課題も深め、法人内やブロック単位での相互評価も始まっています。東京民医連保険薬局委員会委員長の島野清さんに話を聞きました。
指導と薬歴管理に変化 自己点検を通じてみえてきたのは服薬指導と薬歴管理での改善です。これまでありがちだった、薬を渡して説明するだけの「指導」から、S・O・A・P(主訴、客観的情報、分析・評価、治療指針)の手法を用い、患者さんへの傾聴と共感に基づく服薬指導へ。薬歴記載も患者さんを全般的に歴史的にとらえ、サマリーも作成するなど中身の濃いものになりつつあります。
そんなとりくみの中から「し好品の聞き取りが盲点だった。患者さんがしょっぱいものを好きだと知らずに、高血圧の指導をしても効果はあがらないわよね」との声も聞かれるように。
また劇薬・普通薬や向精神薬の分類整理など、薬事法に基づく医薬品の法的整備も改めて見直しました。
薬局機能評価もにらみ
薬局を取り巻く情勢では、医療機能評価の保険薬局版「薬局機能評価」が04年から開始される予定です。一方では社会保険事務局に加えて会計検査院による指導・監査が各地で強化され、特別指導加算や一包化加算など技術料での指導が強められています。きちんとした服薬指導や、日頃からの記録の整備が重要性を増しているのです。
「保険薬局の点検基準作りは3年前から進めていましたが、全体のものにはなりきれていませんでした」と島野さん。この間5回も全体論議を行った法人もあれば、自己点検が済んだばかりのところも。法人間格差はあるものの「今回の自己点検運動で東京民医連全体のとりくみとなったことが大きい。かつてない成果です」と語ります。 集団討議通じ認識深め
こうした自己点検のとりくみの第1次集約にあわせ、11月21日には薬局長研修会を開催し53人が参加。
立川相互病院の大山美宏院長が「医療の安全性と質の向上を目指して」をテーマに、薬局管理者に求められる課題について講演しました。
「薬剤師は医薬品のトータルコーディネーター」との指摘に、参加者からは「薬剤師の意識改革が必要」「患者の権利と安全の視点で、全システムの再構築が必要」などの感想が出されました。
またグループワークでは、先進的な実践やマニュアルを持ち寄り、単なる交流に終わらせず、現場の改善につなげようと真剣に論議が交わされました。
島野さんは「この研修で点検内容でどこが不十分なのか、集団討議を通じて明らかになり、理解度や認識の統一を図ることができた」と。「今後は法人内やブロックでの相互評価が重要です」。
明らかになった課題は多岐にわたります。禁忌の薬剤のくみあわせに対する疑義照会の徹底や、不備処方箋への対応など、医療機関への申し入れが必要な事項もあります。薬剤知識を高め、患者さんから情報を引き出す力量の向上やそのための研修開催、地域要求に合わせた開局時間の延長、夜間・休日の対応など。
「発想を一から変え、医療・福祉宣言に基づいた医療をやろう。そんな薬局も現れています」と語る島野さん。「安全性を確保しながら、患者さんにとって役立つ薬局に変われるかどうか。これからが本当の正念場ですね」。
|