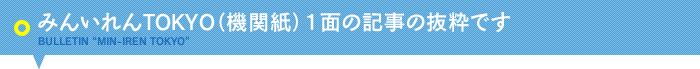医療介護は政治の力で守れる!
参議院選挙で医療・社会保障を充実する政治を!
医療介護は政治の力で守れる!
参議院選挙で医療・社会保障を充実する政治を!
医療機関の危機的な経営状況の背景に政府の医療政策があります。社会保障の充実は参議院選挙の大きな争点です。職員の皆さんに考えていただく材料として、政府の社会保障抑制政策についてまとめました。(編集部)
はじめに
今年の春闘で、医療従事者の賃上げは定期昇給や手当を含めても昨年より3000円程度低くなっており、他産業との格差は昨年以上に広がっています。その背景にあるのが、昨年の診療報酬改定以後、病院をはじめとする医療機関の経営状況が急速に悪化していることです。
2023年度、すでに5割の病院が赤字です。2024年度には医業利益が赤字の病院が69%、経常利益が赤字の病院が61%に達しています。特に給与費、診療材料費、委託費、水光熱費などの経費が軒並み増加しており、診療報酬による収益の増加率(1・9%)では赤字になるのは当然です。一般の企業では債務償還年数(借入の返済に要する年数)が10年程度を超えると破綻懸念企業とされますが、30年を超える病院が50%にのぼっています。
病院6団体と共に記者会見を行った日本医師会の松本会長は「これまでも『地域医療崩壊の危機的状況にある』と繰り返し訴えてきたが、今こそ医療界が一致団結して、著しくひっ迫した医療機関の状況を国民に改めて切実に訴えていきたい」と述べました。
病院経営悪化の原因は
病院経営悪化の原因について、医師会や病院団体が訴えているのは、第一に、「社会保障関係費の伸びを高齢化の伸びの範囲内に抑制する」とする政府方針(いわゆる「目安対応」)の廃止です。第二に、診療報酬の設定について、物価や賃金の上昇に柔軟な対応ができる新たな仕組みの導入です。「目安対応」とは2012年の「税と社会保障の一体改革」から続く制度で、毎年の経済財政運営の基本方針(「骨太の方針」)に基づき、社会保障関係費の伸びを高齢化に伴う自然増の範囲内に抑制するために、診療報酬引き下げなど制度改革を行ってきたことです。こうしたことを毎年繰り返してきました。これまではデフレ経済で賃金も物価も上がらなかったので、医療機関も何とかやってきましたが、物価高騰で全く条件が変わりました。診療報酬が物価の値上がりに対応できなくなっています。
そもそも、社会保障費が伸びているのは、高齢化によるものが三分の一、医学などの進歩によるものが三分の二であり、それを高齢化の伸びだけに抑えることが誤りです。かつて、厚労省やマスコミは「2025年に国民医療費は141兆円になる」と医療費膨張危機を煽ってきましたが、実際には2022年度で46・7兆円です。医療機関の経営改善には、「目安対応」の廃止と診療報酬を物価や賃金の上昇に応じて適切に対応する仕組みの導入がどうしても必要です。
厚生労働省のごまかし
こうした主張に対して、「高齢化が進むので、ある程度の抑制は仕方ない」と思われる方もいらっしゃると思います。本当にそうなのか、考えてみたいと思います。
要介護認定率は年齢とともに上昇し、特に85歳以上は2022年で57・7%です。団塊の世代が後期高齢者となる2025年以降、75歳以上の人口増は緩やかになり、85歳以上の人口が増えつづけるのも2040年頃までです。厚生労働省は2050年には1人の65歳以上の高齢者を20歳から64歳までの1・3人が支える「肩車型社会」になると宣伝しています。しかし、社会保障制度は年齢区分だけでなく複眼的に見る必要があります。女性や高齢者の就労率が高くなっていくことが予測される中では、労働力人口扶養比率でみると2050年も現在とほとんど変わらず、2人で4・1人を支えています。「肩車」ではありません。
経済効果も高める
社会保障の充実
高齢者の医療費が高すぎるとの見方もあります。一人あたりの後期高齢者の医療費は74歳以下と比較して3・9倍、入院で6・5倍、外来で2・9倍です。しかし、入院1件あたりの日数は1・4倍とあまり変わらず、1日あたりの医療費は0・8倍でむしろ現役世代の方が濃厚な医療を受けています。違うのは入院受診率の高さで現役世代の6倍です。これはある意味当たり前です。外来も同じで、受診率は2倍ですが1件あたりの医療費に大きな差はありません。対策は高齢者の健康づくりです。医療費抑制策として窓口負担を増やすことは、かえって健康づくりを妨げ、逆効果です。
国際比較からも、日本は高齢化が最も進んでいる一方で、社会保障費のGDP比率は他の先進国より低く、特に高齢者医療に対する支出は最少水準です。「日本の高齢者は優遇されすぎている」という見方はフィクションです。社会保障費のGDP比率は「自己責任の国」と言われる米国の24・1%より低い、22・8%です(2019年GDP比率)。
2040年には、全体の就労人口が減少する中で医療・介護従事者の確保が課題になります。厚生労働省は、高齢者の就労促進やボランティアの活用、単位時間あたりのサービス提供の5%「改善」(医師は7%)で乗り切ろうとしています。労働強化の危険があり、医師の働き方改革に逆行し、現場で奮闘する医療・介護従事者の気持ちを逆なでするものです。社会保障を抑制するのではなく、充実させ、そこで働く人の処遇改善を行うことこそ、日本の経済を支え、社会全体を支えることになります。社会保障の充実は経済効果も高めます。
税金の集め方、
使い方を正す
そのためにも、税金の集め方、使い方を改めるべきです。集め方では、大企業は法人税減税と優遇税制で、2023年度は11兆円の減税となりました。所得税でも年収1億円を超えると負担率が下がるいわゆる「1億円の壁」の問題があります。使い方では、2025年度予算では、防衛関係費は9・5%増に対して社会保障費は1・5%増、文教科学費は1・4%増、食料安定供給のための予算は0・1%減です(図2参照)。今、多くの人が求めている消費税減税は110か国の国が実施にふみ出しています。
7月に行われる参議院選挙は、これらのことを国民に問う絶好の機会です。